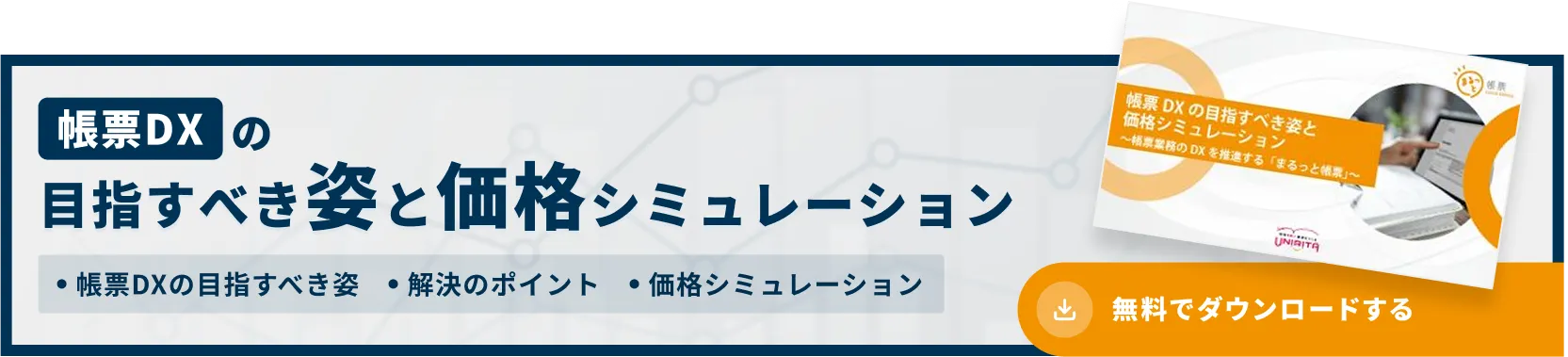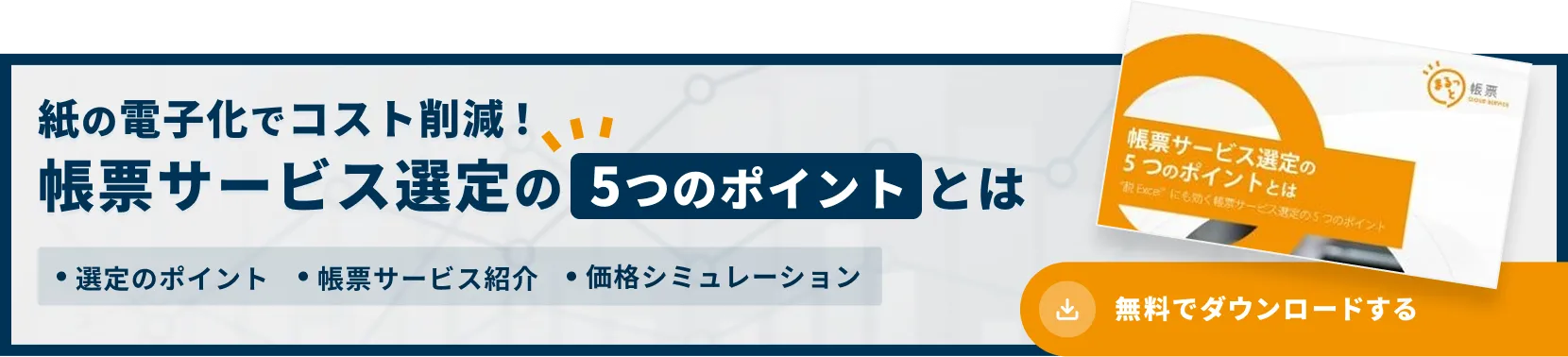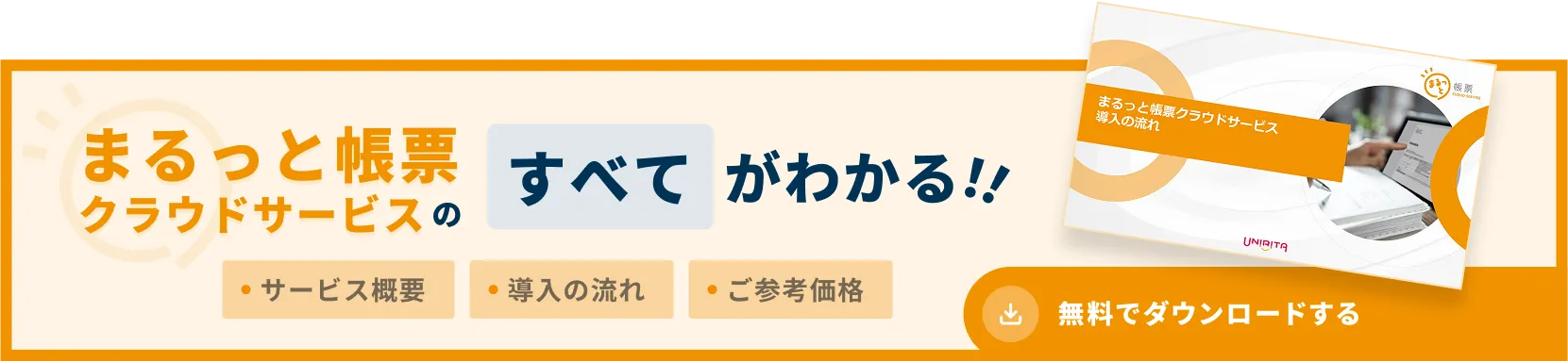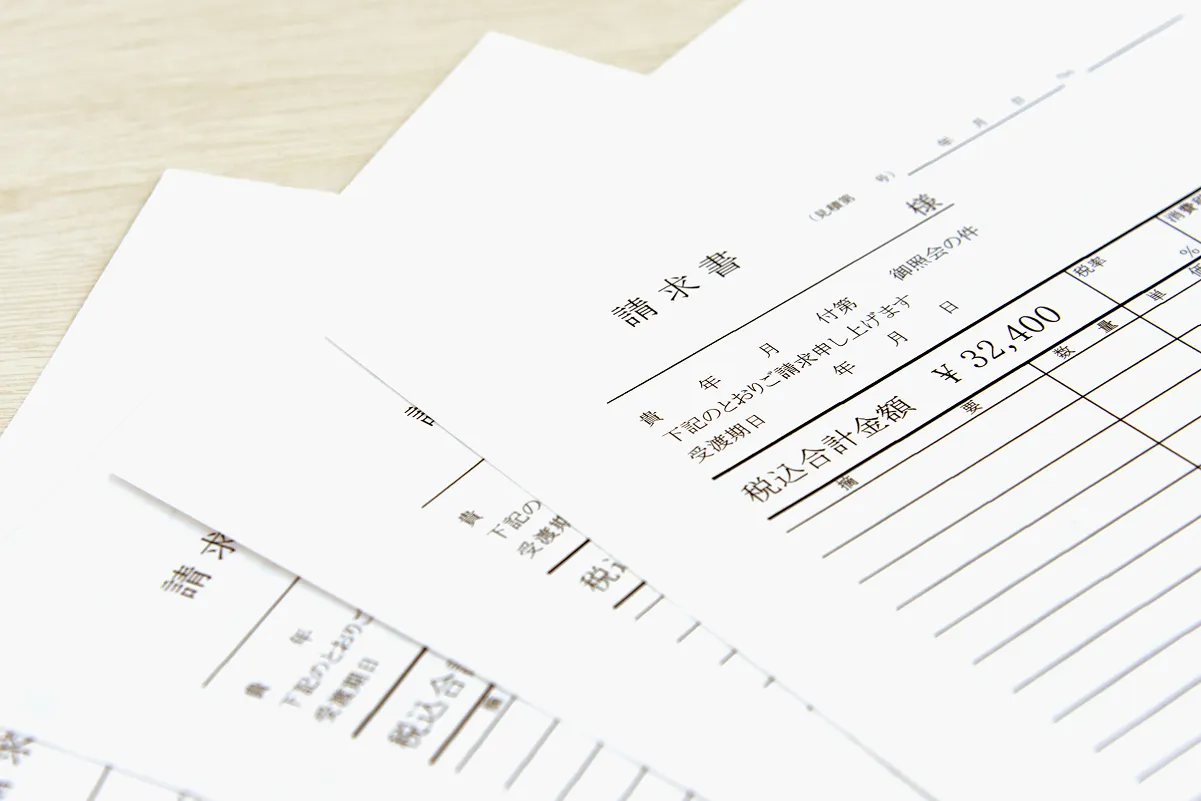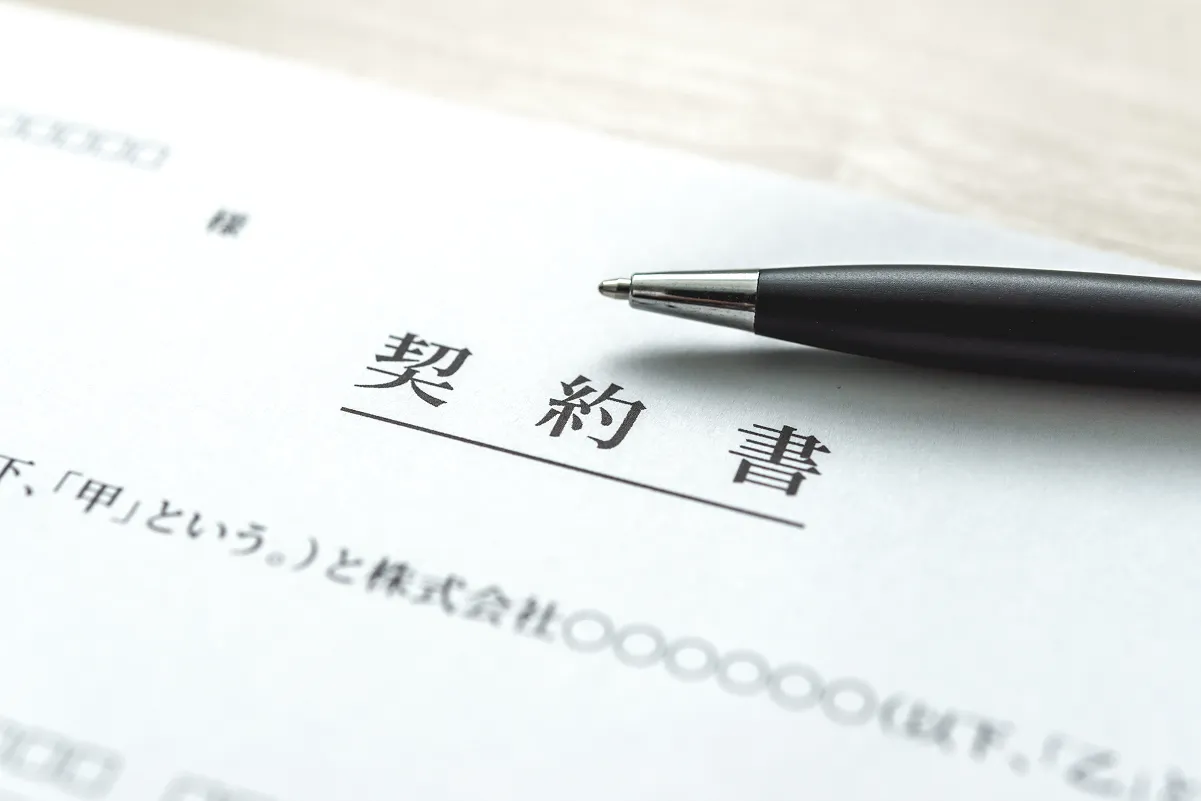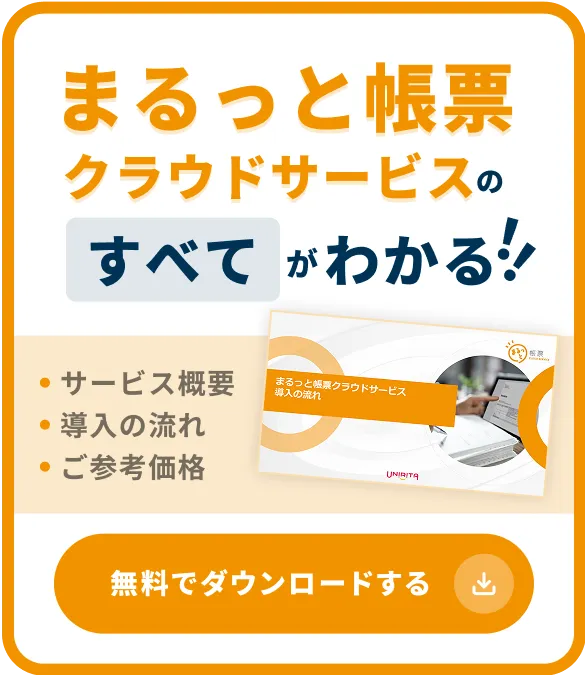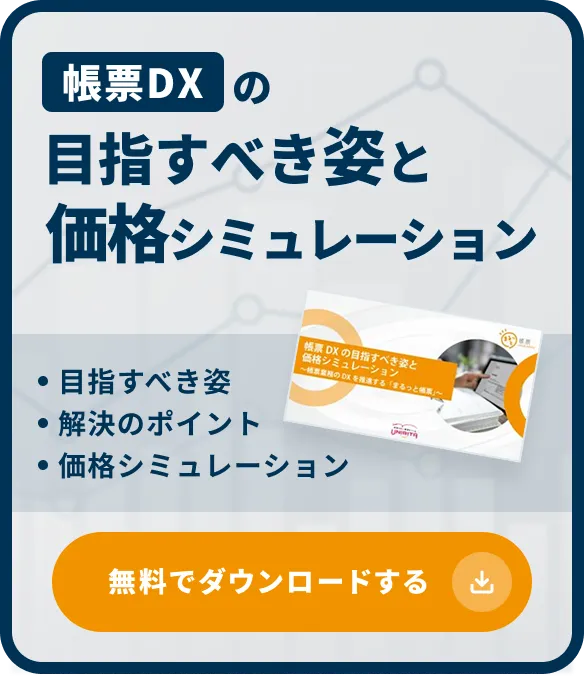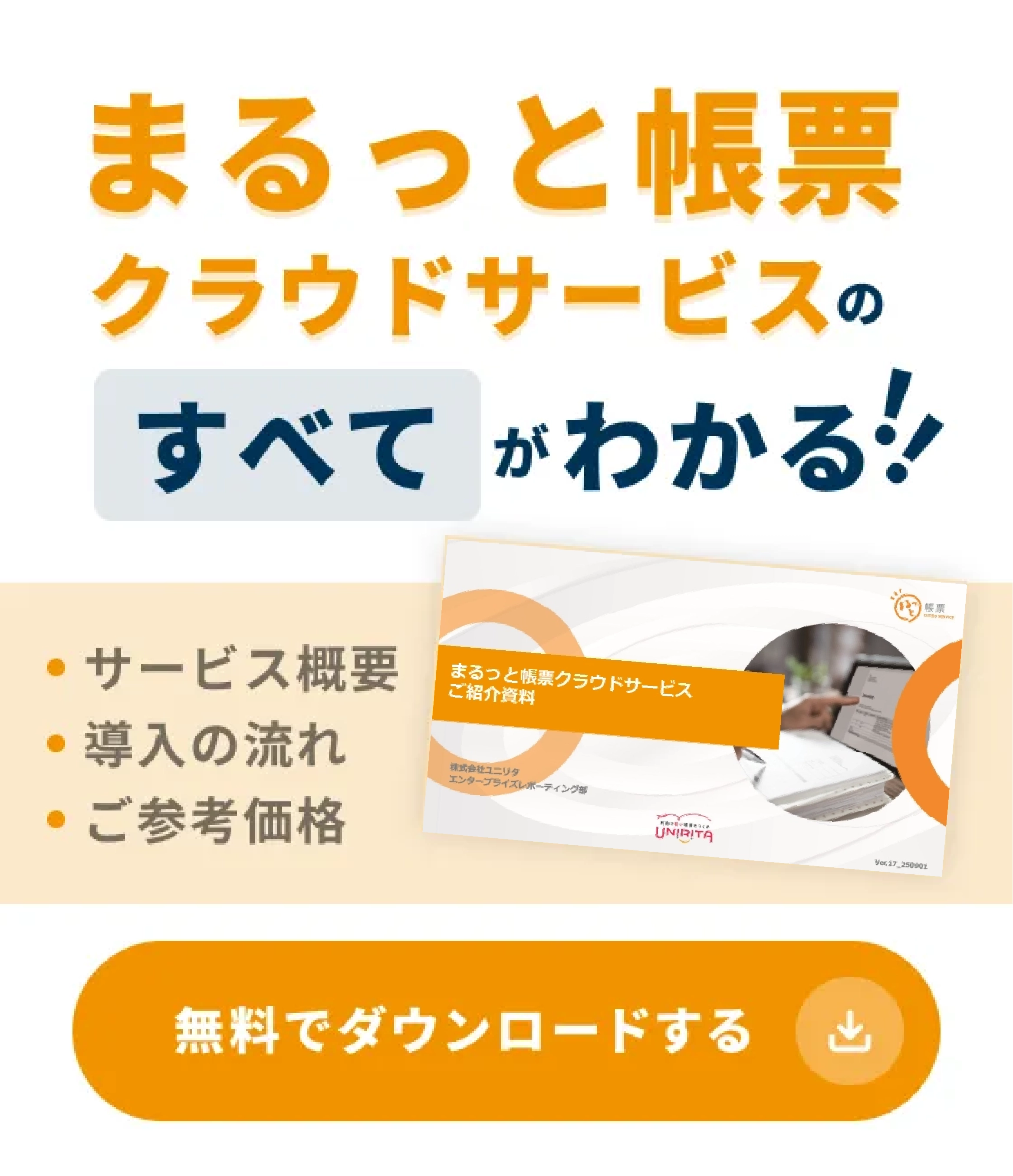記事公開日:
最終更新日:
見積書は電子化しても有効?電子帳簿保存法への対応と注意点を解説

「見積書の電子化って、法的に大丈夫なの?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
2022年1月に改正された電子帳簿保存法により、多くの企業で帳票の電子化への対応が急務となっています。
しかし、単に紙を電子データに置き換えれば良いというものではありません。
電子化した見積書が法的に有効であるためには、電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
本コラムでは、見積書を電子化する際の電子帳簿保存法への対応と注意点について詳しく解説します。
見積書は電子化(PDF)しても法的に有効
結論からいうと、見積書を電子化(PDF形式など)しても法的に有効です。
ただし、法的な有効性を確保するためには、2022年1月に改正された電子帳簿保存法の要件を満たす必要があります。
電子帳簿保存法は、帳簿や書類を電子データで保存することを認める法律であり、これにより企業は紙媒体での保存に代わり、電子データでの保存が可能となりました。
見積書も電子帳簿保存法の対象となる「重要書類」に該当するため、電子化して保存する際には、以下の要件を満たすことが求められます。
主に「真実性の確保」と「可視性の確保」の2つの側面から要件が定められています。
見積書の電子化に必要な要件「真実性の確保」と「可視性の確保」
見積書の電子化に必要な2つの要件「真実性の確保」と「可視性の確保」について、詳しく見ていきましょう。
真実性の確保
真実性の確保とは、保存された電子データが、作成された時点から改ざんされていないこと、そして必要に応じてそのデータが本物であることを証明できる状態にあることを指します。
具体的には、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
タイムスタンプが付されたデータを受領する
タイムスタンプとは、そのデータが特定の時刻に存在し、それ以降、改ざんされていないことを証明するものです。
取引相手から電子データを受け取る際に、すでにタイムスタンプが付与されている場合は、そのデータをそのまま保存することで真実性の要件を満たすことができます。
速やかにタイムスタンプを付与する
もしタイムスタンプが付与されていない電子データを受け取った場合は、自社で速やかにタイムスタンプを付与する必要があります。
この「速やかに」とは、「概ね7営業日以内(早期入力方式)」か「最長2ヵ月を経過後、概ね7営業日以内(業務サイクル方式)」のいずれかとなっています。
データの訂正・削除の履歴が残る、または訂正・削除ができないシステムを利用する
電子帳票システムの中には、データが一度保存されると訂正や削除ができない、あるいは訂正・削除の履歴がすべて記録される機能を備えているものがあります。このようなシステムを利用することも、真実性確保の要件を満たす有効な手段となります。
これにより、人為的なミスや意図的な改ざんを防ぎ、データの信頼性を高めることができます。
逆に、WordやExcelのように後から編集が可能なファイル形式では改ざんの恐れがあるため、真実性の確保に該当しません。
不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて運用する
上記のようなシステムを利用しない場合でも、自社内で不当な訂正・削除を防止するための事務処理規程を定め、その規程に従って運用することで真実性の要件を満たすことができます。
具体的には、「取引について相互のけん制が機能する体制であること」などの内容を盛り込む必要があります。
詳細については、国税庁の該当ページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/980528-4/02.htm
可視性の確保
可視性の確保とは、保存された電子データが、税務調査などで必要とされた際に、速やかに閲覧・確認できる状態にあることを指します。
これは、電子データのアクセス性を保証するための要件です。
保存場所へのPC、ディスプレイ、プリンター等の設置
電子データを保存している場所には、そのデータを閲覧するためのPC、ディスプレイ、そして必要に応じて印刷するためのプリンターなどの機器を設置しておく必要があります。
こうすることで、いつでも電子データを確認できる環境が整っていることを示せます。
システムの概要書を備え付ける
さらに、利用している電子帳票システムの概要書や、データの入出力処理に関する書類などを備え付けておく必要があります。
こうして、システムの全体像やデータの流れを第三者が理解できるようにします。
検索機能の確保
保存された電子データは、取引年月日、勘定科目、取引金額などの主要な項目で検索できる状態にしておく必要があります。
さらに、日付や金額の範囲指定、複数の条件を組み合わせて検索できる機能も求められます。
これにより、膨大な電子データの中から必要な情報を迅速に探し出すことが可能となり、税務調査などの際にスムーズな対応が実現します。
見積書を電子化するメリット
見積書の電子化は、単に電子帳簿保存法に対応するだけでなく、企業に様々な業務効率化とコスト削減のメリットをもたらしてくれます。
見積書作成から送付までの時間を大幅に短縮できる
紙の見積書の場合、作成、印刷、押印、封入、郵送といった一連の作業に多くの時間と手間がかかります。
これが電子化されることで、システム上で作成・承認・送付までを一貫して行うことが可能になります。
特に見積書関連業務に複数の部門が関わる大手企業においては、ワークフローの電子化により承認プロセスが迅速化され、顧客への見積書提出までのリードタイムを大幅に短縮できるため、商機を逃すことなく、ビジネススピードの向上につながります。
検索性が向上し、必要な情報を迅速に探し出せる
紙の見積書は、ファイリングして保管する必要があるため、過去のデータを探すのに手間がかかり、さらには紛失のリスクも伴います。
一方、電子化された見積書なら、日付、取引先名、金額など、さまざまな条件で瞬時に検索することが可能です。
このため、顧客からの問い合わせに対する迅速な対応や、過去の取引履歴に基づいた分析など、必要な情報を必要な時にすぐに活用できるようになります。監査対応時などに大量の書類の中から該当データを探し出す負担が軽減されます。
ペーパーレス化でコスト削減できる
見積書の電子化は、直接的なコスト削減にもつながります。
印刷用紙代、インク代、封筒代、郵送費といった消耗品費や通信費が不要になります。
さらに、見積書を保管するためのファイルやキャビネットなどの備品代、そして保管スペースの賃料も削減できます。
これらのコストが積み重なると相当な金額になるため、ペーパーレス化によるコスト削減効果は非常に大きいものがあります。
削減できたコストは、ほかの戦略的な投資に充てることが可能です。
見積書を電子化するにあたっての注意点
見積書の電子化は多くのメリットをもたらしますが、その運用にあたってはいくつかの注意点があります。
編集・変更が困難な形式(例:PDF)で電子化する
「データの訂正・削除の履歴が残る、または訂正・削除ができないシステムを利用する」でもお伝えした通り、電子帳簿保存法の「真実性の確保」の観点からも、電子化した見積書は容易に編集・変更できない形式で保存することが重要です。
たとえばPDF形式には、一度、作成されると内容の改ざんが難しいという特性があり、見積書の電子化に適した形式といえます。
逆にExcelやWordなどの編集可能な形式で保存した場合、意図しない修正や悪意のある改ざんのリスクが高まり、証拠能力が損なわれる可能性があります。
専用の電子帳票システムを利用することで、よりセキュアな形式での保存と管理が可能になります。
見積書の有効期限を明記する
電子化された見積書であっても、その有効期限を明確に記載することは重要です。
有効期限の曖昧さによるトラブルを避けるためにも、従来の紙の見積書と同様に、有効期限の明記は必須といえるでしょう。
有効期限が不明確だと、後のトラブルの原因となる可能性があります。
顧客が見積書の内容をいつまで有効と認識しているのか、企業側がいつまでその内容を保証するのかを明確にすることで、双方の誤解を防ぎ、スムーズな商取引につながります。
有効期限は、見積書作成時にシステム上で自動的に付与されるように設定することも検討しましょう。
記載内容とファイル名に相違がないか確認を行う
前提として、電子化された見積書は、大量のデータとして保存されるため、適切なファイル名をつけることが重要です。
ファイル名には、取引先名、案件名、日付など、内容を容易に判別できる情報を盛り込むべきです。
その上で、ファイル名と実際の記載内容に相違がないかを必ず確認しましょう。
この確認を怠ると、必要な見積書を迅速に検索できなかったり、誤った見積書を参照してしまったりする恐れがあります。
見積書の電子化には帳票システム「まるっと帳票クラウドサービス」がおすすめ
見積書の電子化を進める上で、電子帳簿保存法への対応や既存システムとの連携など、情報システム部のご担当者様が抱える課題は多岐にわたります。
そこでおすすめしたいのが、「まるっと帳票クラウドサービス」です。
既存データをそのまま活用し、導入負荷を最小限に
「まるっと帳票クラウドサービス」は、お客様が現在お使いの帳票データをそのまま活用できるクラウドサービスです。データ加工、帳票生成、電子化、Web配信までをワンストップで提供し、既存システムからのスムーズな移行と導入負荷の軽減を実現します。もちろん、電子帳簿保存法などの法的要件にも準拠しているため、安心してご利用いただけます。
これにより、お客様の企業全体として業務効率を最大化、ご担当者様の負担を軽減しながら生産性向上を叶えます。
まとめ
見積書を電子化することで、業務効率化、検索性の改善、コスト削減など、さまざまなメリットが得られます。
ただし、電子化を進めるにあたっては、電子帳簿保存法に定められた「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件を確実に満たす必要があります。
これらの法的要件を遵守し、スムーズに電子化へ移行するためには、「まるっと帳票クラウドサービス」のような電子帳票システムの活用が効果的です。既存の帳票データをそのまま活用できるため、導入負担を抑えつつ、法令に準拠した効率的な帳票管理を実現できます。
詳しくは、下記の公式サイトをご覧ください。
https://marutto-chohyo.unirita.co.jp/
資料ダウンロード
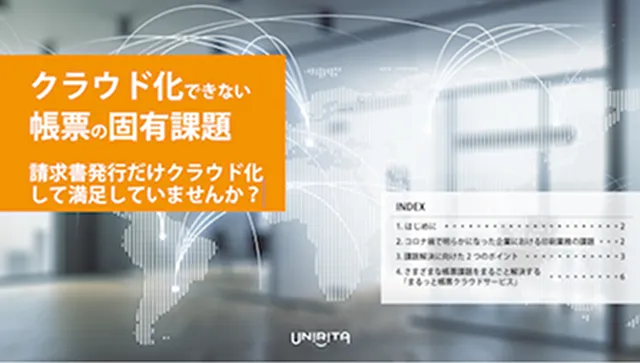
クラウド化できない帳票の固有課題
請求書発行だけクラウド化して満足していませんか?
執筆者情報

小柳 晶(こやなぎ あきら)
株式会社ユニリタ セールスプランニングディビジョン
ユニリタの前身である(株)ビーエスピーに開発者として入社。自社プロダクトの開発、自社製品周辺のシステム構築、受託開発のPM、セールスエンジニアを経験し、特に帳票業務運用に精通。電子帳簿保存法対応やペーパーレス化、印刷業務の効率化などシステム構築だけでなく、その先の運用を見据えた幅広い業務改善を100社に及ぶ企業に実施。現在は帳票プロダクトのクラウドサービス化企画に従事する傍ら、帳票運用や運用改善のコラム執筆・セミナー登壇も行っている。